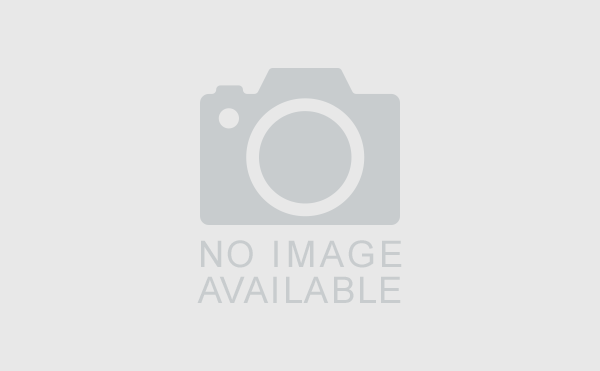【司法試験】刑法(H19)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F31322D985F95B68EAE8E8E8CB196E291E881698A6D92E894C5816A>)】
答案(例)
第1 甲の罪責
1.Aから20万円を交付させた行為
(1)詐欺罪
ア.●論証:要件
イ.あ:…。脅されたからなので未遂(250条、246条1項)
(2)恐喝罪
ア.構成要件該当性
(ア)定義
(イ)あ:該当
イ.違法性
(ア)●論証:権利行使と恐喝
(イ)あ:
ウ.成立(249条1項)
2.Aから100万円を交付させた行為
(1)詐欺罪は不成立(欺罔行為なし)
(2)恐喝罪
畏怖は継続しており成立。違法性阻却されない点は同上。よって、成立。
3.50万円を費消した行為
横領罪(252条)該当性が問題。
(1)構成要件:各種定義 ●論証:民法との整合性(●不法原因も?)
(2)あ:
(3)結論:成立
なお、50万円しか受け取れなかったとの虚言は、横領の手段に過ぎず、詐欺利得罪不成立。
4.罪数
同じ法益に向けられた詐欺罪は恐喝罪に吸収され、詐欺罪と横領罪は併合罪(45条前段)。
第2 乙の罪責 ●留意:参考判例を引きつつ。
1.Aに20万円を交付させた行為
●論証(軽く):共同正犯の要件
・恐喝罪の共同正犯(60条1項、249条)。
2.甲がAに100万円を交付させた行為
事例の問題提起
(1)●論証:共犯関係の解消
(2)あ:解消〇
3.罪数:上記第2の1.記載の1罪のみ。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F31322D95BD90AC82508258944E90568E6996408E8E8CB1985F95B6>)】
採点実感等
・該当なし
・ヒアリング
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F31322D83718341838A8393834F8A54977688C481698C598E968C6E>)】
参考
・故意の検討も軽くは。客観的構成要件要素のみではなく。
その他
・論証は薄くてOKな模様。それより定義等がきっちりかけることが重要なのだろう。