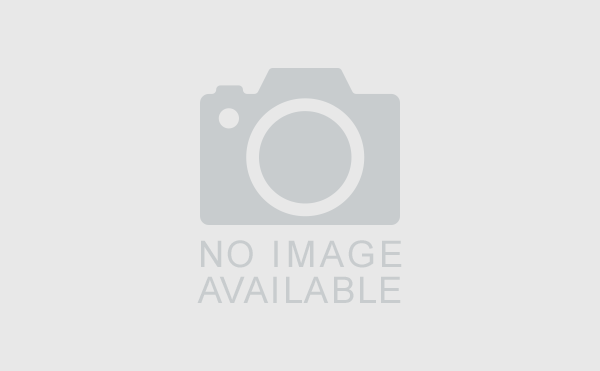民事訴訟法
「…公法の抵触問題と私法のそれとはその性質が大いにちがうものであるから、…国際私法の範囲から除外するのが妥当である。」
(江川英文『国際私法(改訂)』(有斐閣、1957)17頁)
知識・留意点
・訴訟能力等を欠く場合の措置等(34条)
・訴訟手続の中断及び受継(124条):「死亡」とあれば意識する。
・中断及び中止の効果(132条)
・口頭弁論を経ない訴えの却下(140条)
・「追って敗訴した●から担保責任(民法565条)を追及される可能性があることから、補助参加する必要がある。」等の理屈あり。
訴訟法上の行為と意思表示の瑕疵・欠缺
・管轄合意:訴訟外で取引等に付随してなされることから、訴訟手続の安定を害しない。よって、民法の規定が(類推)適用される。
当事者の確定
当事者の確定の基準が問題となる。
当事者は、人的裁判籍(4条)等の基準となることから、合理的な形で早期に明確となる必要がある。
そこで、原則として訴状上の当事者(133条2項1号)記載を基準とし、請求の趣旨・原因等を踏まえた合理的な解釈をすべきである。
当事者(となるはずだった者)の死亡
【原告】
1.訴え提起前に死亡
(1)訴訟継続前に発覚
【論点】当事者の確定→(当事者の記載を欠くとして)補正命令(137条1項)→(不能なら)訴え却下(同条2項)
(2)訴状送達後口頭弁論終結前に発覚(前提:実質的に相続人を指すと解釈可能なら表示の訂正でOK):
ア.【論点】当事者の確定→原則として訴え却下→しかし訴訟代理人選任後の死亡であれば訴訟維持(124条1項1号、2項類推)。
イ.【論点】当事者の確定→原則として訴え却下→しかし相続人への任意的当事者変更がされれば訴訟維持。されなくとも、訴訟行為の無効主張等は、当事者間の公平上、信義則(2条)に反する。
2.訴え提起後に死亡:上記1(1)同様である他、それ以降は、当然承継(●条文?)、及び中断・受継(124条1項1号等)の話。
【被告】
債務不存在確認訴訟
・訴訟物が特定されているといえるか。
債務不存在確認訴訟は給付訴訟の反対形相であるから、その訴訟物は、債務全額から自認額を控除した残額と解される。
・上限を明示していない場合
請求原因・一件記録から上限を判断できる場合には、特定性を充足すると解される。
債権者代位訴訟
・債務者による独立当事者参加(権利主張参加)(47条後段)
1.二重起訴の禁止(142条):併合審理・合一確定されるので問題なし。
2.当事者適格(民法423条の5)
3.独立当事者参加の要件(論理的非両立)
・他の債権者が既に債権者代位訴訟を提起していた場合、①共同訴訟参加(52条1項)、又は②独立当事者参加(権利主張参加)(47条後段)が考えられる。
二重基礎の禁止(142条)
…は…なので二重起訴の禁止(142条)により不適法却下されないか、「事件」の同一性判断基準が問題となる。
同条の趣旨は、矛盾判決、被告応訴の煩、訴訟不経済の回避にある。
そこで、「事件」の同一性は、訴訟物・当事者を基準とするものと解される。
1.抗弁先行型
・問題点:「事件」(142条)ではない。
・
2.訴え先行型
・問題点:「訴え」(142条)ではない。
訴訟判決と既判力
・問題点:既判力は訴訟物につき生じるところ、訴訟判決は訴訟物に係る判決ではない。
そもそも既判力の趣旨は、手続保障を前提とした紛争の蒸し返し防止にある。
訴訟要件に存否についても、それらは妥当する。
よって、訴訟判決に既判力は生じると解される。
処分権主義(246条)
・趣旨:当事者への不意打ち防止
・要件(一部判決):原告の合理的意思に反せず、かつ被告への不意打ちとならない限り、認められる。
確認の訴え
・問題点:対象無限定、執行力なし
そこで、紛争解決の実効性のため、確認の利益が必要。
具体的には、①対象選択の適否、②即時確定の利益、③方法選択の適否につき判断される。
債務不存在確認訴訟の場合、①消極的確認ではあるが、現在の法律関係の確認であり、対象選択は適切である。また、②地位の不安定さから、即時確定の利益も認められる。さらに、③債務者は給付の訴えを提起できず、方法選択についても適切である。
よって、確認の利益を有し適法である。
・
固有必要的共同訴訟(40条)
・判断基準が問題となる。
この点、民事訴訟は実体法上権利の実現のための手続である一方、当事者適格は訴訟追行権という訴訟上の権能の問題でもある。
そこで、訴訟物たる権利・法律関係の実体法上の性質を中心に、紛争解決の実効性等の訴訟法上の要請との調和の見地から決せられると解される。
組合
・固有必要的共同訴訟
・選定当事者(30条):〇
・任意的訴訟担当:〇
●検討:当事者能力との関係
明文なき任意的訴訟担当
・いわゆる三百代言の禁止にある。
・そこで、弁護士代理の原則(54条1項本文)や訴訟信託の禁止(信託法10条)の趣旨に反せず、これを認める合理的必要性があれば、許容されると解される。
訴訟要件の審理・資料収集
・抗弁事項⇔職権調査事項
・弁論主義⇔職権探知主義
訴訟要件の存否不明の間の請求棄却判決
・訴訟要件の趣旨次第
・訴訟要件は本案判決のための要件である。という点を重視すれば、画一性・明確性のため、不可。
・債権者代位訴訟の場合、特に不可、だろう。訴訟要件こそが肝であり、債務者の利益保護のため。
客観的併合(予備的併合)
・前提:控訴不可分の原則(●条)
1.主位的請求認容(被告が控訴)
控訴審は(第一審判決を取り消し、主位的請求を棄却した上で)予備的請求について認容できるか。予備的請求について、被告の審級の利益を害するとも思われることから問題となる。
…という客観的予備的請求の性質上、両請求は密接に関連しており、予備的請求についても実質的には審理済みと言える。また、控訴審において訴えの変更が認められることとの均衡から、予備的請求を認めても被告にとり格別の不利益はない。そこで、控訴審は予備的請求について認容することができると解される。
2.予備的請求認容・主位的請求棄却(被告が控訴)
控訴審は主位的請求について認容できるか。
処分権主義(246条)の下、不利益変更の原則(304条)。
かかる認容は、被告にとり原判決より不利である。
よって、主位的請求は控訴審の審判対象にはならないと解される。控訴審は、第一審判決を取り消し、予備的請求について請求棄却判決をすべきである。
(この点、主位的に請求については売買契約が無効であるとして、また予備的請求については売買契約が有効であるとして、棄却されることとなり、原告に酷とも思われる。しかし、原告としては、主位的請求棄却判決に対し、控訴又は付帯控訴できたのであるから、酷ではないと考える。)
●認識:いずれも認容されることはなく、いずれも棄却された場合は問題がない。
独立当事者参加(権利主張参加)(47条後段)
・趣旨:
・要件:論理的非両立 ●問題点:訴訟物の?当事者適格の?請求の趣旨の?
・債権者代位訴訟に参加する債務者については、前2者が認められないが、請求の趣旨は論理的非両立といえる。よって、当該要件充足。
・「効力」(48条後段)の意義が問題となる。脱退は、自己の立場を参加人と相手方との間の勝敗に委ね、各々との間において請求の放棄・認諾をする趣旨と解される。そこで、「効力」とは、それらの効力、及びそれらに応じた既判力・執行力をいうと解される。
控訴の利益
判断基準が問題となる。
全部勝訴の場合、不服を認めるのは自己責任原則に反する。また訴訟手続きの安定のため形式的に画する必要がある。
そこで、当事者の申立内容と現判決の主文を比較し、後者が前者に及ばない場合に認められると解される。
●
・

日本の民事訴訟法は「全く知らない」というのもマズイかと考えまして、試みに…

「『全く知らない』訳ではない」ということだけは、かろうじて理解できました(笑)。