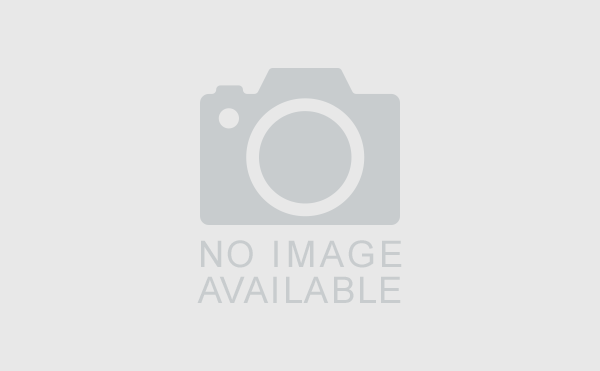民法(財産法)
「…公法の抵触問題と私法のそれとはその性質が大いにちがうものであるから、…国際私法の範囲から除外するのが妥当である。」
(江川英文『国際私法(改訂)』(有斐閣、1957)17頁)
【総則】
思考方法・基礎知識
・一般法人法:理事の代表権の制限(77条5項)、法人の不法行為(78条)理事会の承認(90条4項)、対第三者責任(117条1項)
・表見法理(趣旨)フレーズ:「①虚偽の外観を②作出した本人の負担の下、③第三者の取引の安全を保護する」(ポイント:①外観の存在、②本人の帰責性、③相手方の信頼)
・取消しの遡及効(121条)
・107条
・101条
94条
・「第三者」(94条2項):虚偽表示当事者を保護する必要性は低いことから、無過失不要。同じく登記も不要。
・善意の前者が担保責任(565条)の追及を受けないよう、転得者は悪意でも保護される。
・類推:通謀はない。しかし、趣旨から。
・本人の帰責性が小さい場合、第三者の信頼要件を厳しくし、バランスを取る。例:110条類推(外形意思非対応型)●方針:判例は110条の法意、とするが、類推でOK
95条
・基礎事情錯誤:
①「認識が真実に反する」(95条1項2号)●補足:あてはめEASY
②「重要」(95条1項柱書):相手方保護のため「社会通念」に照らすことから、表意者のみならず、一般人も本来意思表示をしなかったであろう場合をいう。
③「表示」(95条2項):相手方保護の趣旨から、相手方に了解されていることまで要する。
・「第三者」(95条4項):趣旨から、取消前の第三者
・債権者代位:原則表意者等のみ(120条2項)。しかし、債権者の期待は正当。また、無資力・不履行の債務者の意思尊重の必要性低い。よって、行使上の一身専属性は否定され、許容される。
96条
・趣旨(96条3項):詐欺による意思表示を信頼した第三者の取引の安全を保護するため、取消しの遡及効を制限する。
・「第三者」(96条3項):趣旨から、詐欺取消し前の第三者をいう。
・登記:被詐欺者の帰責性とのバランス上、不要。
・取消後の第三者:取消後に登記をせず放置していた点、二重譲渡同様の状況にあることから、対抗問題となる。●補足:動産は192条の可能性あり。前後問わず。●検討
有権代理
・法的性質:当事者の合理的意思から、事務処理契約説(自説)
・取消し(本人):表見代理規定の類推適用
・取消し(代理人):①代理人に不利益はなく、基本的には不要(5条1項ただし書き類推)、②認める場合でも表見代理既定の類推適用(●方針:遡及効を否定し将来効とする根拠には乏しいだろう。 )。
表見代理
・本人名義:趣旨から帰属する。 法律構成は「類推」。
・「第三者」:趣旨から代理権への信頼保護にあり、通常かかる信頼をする直接の相手方に限る。
日常家事債務(761条)
・趣旨:日常家事処理の便宜
・代理権:趣旨から、連帯責任の前提として、代理権まで付与したものと解される。
・「日常の家事」(761条本文):夫婦の共同生活に通常必要な行為であり、夫婦の内部事情・行為の目的の他、第三者保護のため、客観的な法律行為の種類・性質等を考慮して判断される。
・110条との関係:夫婦の財産的独立(762条1項)を維持するため直接適用は否定するも、相手方の取引の安全を保護するため、相手方において行為が当該夫婦の日常家事に属すると信じるにつき正当の理由がある場合、110条の趣旨を類推適用する。
無権代理と相続
・無権代理人の本人相続:無権代理人の地位と本人の地位は併存(通説)。●判例:融合だが。しかし、無権代理人が自ら追認拒絶は信義則(1条2項)違反。よって、追認拒絶できない。
・無権代理人と共同相続:本人の追認権は共同相続人全員に不可分的に帰属する。よって、全員の追認がない限り、無権代理人の相続分についても当然有効になるものではない。●理解:追認拒絶も信義則(1条2項)に反しない。
・本人の無権代理人相続:地位併存。追認拒絶ができる。他方、無権代理人の責任(117条)としての損害賠償義務は負担する。
・無権代理人を相続⇒本人を相続:無権代理人の本人相続と同様。
・本人を相続⇒無権代理人を相続:本人の無権代理人相続と同様。
・本人追認拒絶後に無権代理人が相続:本人の追認拒絶により無権代理行為の無効が確定。確定した効果を主張することは信義則(1条2項)に反しない。
・無権代理人(本人の後見人となった後)の追認拒絶:成年後見人は本人に対し善管注意義務(869条、644条)を負う以上、原則として、後見人は本人の追認拒絶権(113条1項)を代理行使できる(859条1項)。しかし、相手方保護の必要性・妥当性、被後見人の保護の必要性等を考慮し、信義則(1条2項)に反する場合には、例外として、追認拒絶は認められない。
●補足:他人物売買も同様。
無効・取消し
・121条の2:「無効」には、遡及的無効(121条)の場合を含む。よって、制限行為能力者・詐欺・双務契約の無効・取消し等に共通して適用される。●補足:危険負担ではなく、不当利得の問題として整理されている。
・取消権の期間の制限(126条)
時効
・趣旨:永続した事実状態の尊重等
・趣旨(援用):利益を得る者の意思の尊重
・「当事者」(145条):趣旨から、時効完成により直接利益を受ける者(●⇔反射的利益を受ける者)に限定される。
・法的性質(援用):「取得する」(162条)・「消滅する」(166条1項、同2項)と定める一方、援用要することとの調和から、時効の効果は援用時に初めて確定的に生じると解される(不確定効果説・停止条件説)。
●29改正:連帯債務者間において、時効の完成は相対効とされた(441条)。●補足:絶対効は、更改(438条)・相殺等(439条1項)・混同(440条)。
・援用権の代位行使(423条):援用の趣旨から否定されるか?錯誤取消し同様の論理で肯定。
・主債務の消滅時効完成後の保証人による一部弁済等の場合の援用の可否:求償権の保護のため、主債務が時効消滅しても支払う意思であった場合でない限り、援用権を失わない。
・物上保証人が被担保債権につき承認をした場合:債務者ではないことから、時効援用は可能。
賃借権の時効取得
・債権ではあるが、継続性・占有を要する点、地上権と同様。そこで、①継続的用益という外形が存在し、②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていれば、「所有権以外の財産権」(163条)として時効取得できると解される。
・抵当権との関係:土地賃借権者が対抗要件を具備する前に土地に抵当権が設定された場合:通常の賃借権の取得についても、抵当権設定登記に先立って対抗要件具備が必要であることと同様。そもそも賃借権と抵当権とは「相容れない権利」ではない。よって、賃借権の時効取得は抵当権者に対抗できない。●補足:所有権の時効取得の場合とは異なる。
時効取得と登記
・時効の起算点は占有開始時。
・時効完成後の譲渡の後、更なる期間占有により時効取得可能。
・時効取得の対象は自己物でも可能であることから、時効完成後の譲受人が登記を経由しても、時効の更新事由とはならない。
●前提:趣旨が妥当すること、及び「他人の物」(162条)に限定する必然性はなく典型的な例示と解されることから、自己物の時効取得可能。
消滅時効
・一部請求と残部債権の時効の完成猶予・更新:(一部請求が明示的か否かに関わらず)一部請求に係る確定判決によっても残部は確定しない。よって、時効の更新は認められない。しかし、訴訟継続中は、残部について権利行使の意思が継続していると考えられる。そこで、特段の事情のない限り、裁判上の請求(147条1項1号)に準じ、時効の完成猶予は認められる。
【物権】
思考方法・基礎知識
・●
「第三者」(177条)
・趣旨(177条):不動産登記の公示により取引の安全を図る。
・定義:趣旨から、「第三者」とは、当事者又はその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者 ●補足:178条も同じ。
・論点(悪意・背信的悪意):趣旨から、単なる悪意者は、自由競争・取引の範囲内にあり、第三者にあたる。背信的悪意者については、その範囲外にあり、あたらない(1条2項)。
物権変動と登記
●基本:(前)条文あれば適用して保護(実体あり、ゆえ登記の話にならず。例:909条ただし書き)。当事者類似の関係(実体あり、かつ登記不要。例:取得時効)。(後)対抗関係と類似
・時効(応用):不動産の取得時効完成後の抵当権設定登記→その後更に取得時効に必要な期間占有→抵当権の存在を容認していた等の事情がない限り、時効取得により抵当権消滅。
・取消し・解除:●●●
・共同相続:無権利者からの譲受けであることから、登記なくして対抗できる(899条の2第1項参照)。
・相続放棄:①相続放棄に期間制限(915条1項)があり、②その有無につき家庭裁判所で調査可能であることから、相続人保護のため遡及効(939条)を貫徹し、登記なくして対抗できる。
・遺産分割(前):第三者保護(909条ただし書き)。●認識:早く遺産分割しないといけない。
・遺産分割(後):対抗関係と類似することから、登記なくして対抗できない。●認識:早く登記しないといけない。
・遺贈:●●●
・遺言(相続させる旨):●●●
即時取得(192条等)
・趣旨:動産占有に公信力を付与し取引の安全を図る。
・要件:①動産、②取引行為、③無権者、④平穏・公然・善意・無過失、⑤占有
・補足:⑤占有については、「外観上占有状態に変更が生じる」がKey Word(例の論点)
・応用:取消し・解除と第三者保護との関係(上記③保護無権者、からの譲受けか?)●方針:Case by Case。
・論点(193条):回復請求可能期間中の所有権の帰属:回復は原始取得していないことが前提なので、現所有者(大判大10.7.8)。192条の趣旨を貫徹し、善意取得者(通説)。●自説:通説(例外、でOK。復帰的物権変動的理解にて。古い判例でもあり。)。
・論点(194条):引渡し拒絶期間中の使用収益権限:代価の弁償の有無次第で権限の有無が決まるのは取得者の保護に欠けることから、あり(判例)。●検討:逆も言えるが。
・趣旨:不動産の附合(242条):復旧に伴う社会経済上の不利益回避。
・論点:建前が第三者の工事により完成した場合、建物への工作は特段の価値を有することから、(附合ではなく)加工についての規定(246条2項)により権利帰属を決するのが妥当と解される。
占有と相続
・論点(前提):占有の相続:社会通念上当然に認められる。
・論点:相続人は「承継人」(187条)にあたるか。187条の趣旨は、占有の二面性を認める点にあり、相続人の場合にも妥当する。
・論点:相続は「新たな権限」(185条)にあたるか。相続につき認識ない権利者保護のため、原則としてあたらない。しかし、相続人保護のため、①新たに事実上の支配をすることで占有開始し、②それに所有の意思がある場合、例外的にあたると解される。
【担保物権】
思考方法・基礎知識
・
留置権
・趣旨:当事者間の公平
・要件:①「その物に関して生じた債権」、②債権が弁済期、③他人の物(以上295条1項)、④占有が不法行為により始まっていない(同条2項)
・解釈:趣旨から、①は、物の留置により間接的に弁済を強制する関係(牽連性)を要する。
質権
・論点:設定者への返還:345条の趣旨は公示の貫徹にある。よって、対抗力を失うに過ぎない(判例)。●検討:345条の趣旨は留置的効力の確保にある。よって、質権自体が消滅する(通説)。●方針:判例
抵当権
・

日本の民法(財産法)は「全く知らない」というのもマズイかと考えまして、試みに…

「『全く知らない』訳ではない」ということだけは、かろうじて理解できました(笑)。