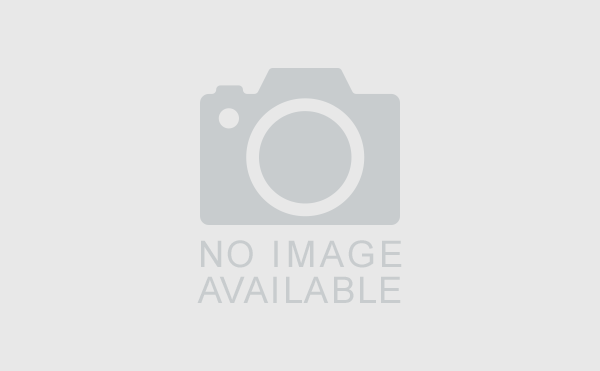【予備試験】刑事訴訟法(令和5年)
問題
次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
1 司法警察員Pは、令和4年7月1日にH県内の飲食店で甲が同店店員の顔面を殴打した(以下「本件暴行」という。)という事件を捜査し、甲を逮捕することなく、H地方検察庁検察官Qに同事件を送致した。しかし、甲は、まもなく所在不明となった。
2 その後、同年8月20日、H県内で、V方に何者かが侵入し、Vの顔面を多数回殴打してその両手両足をひもでしばるなどの暴行を加え、V所有の高級腕時計を奪い、その際、Vに傷害を負わせた(以下「本件住居侵入・強盗致傷」という。)という事件が発生した。そして、Vの供述等から、実行犯は1人であることが想定された。Pは、同事件が発生した直後、実行犯とは容ぼうが異なる甲が同腕時計を中古品買取店に売却した事実を把握し、甲が同事件の実行犯と共犯関係にあるとの嫌疑を抱いた。なお、捜査の過程で、甲の所在は判明したが、実行犯の氏名や住居等は判明しなかった。
そこで、Pは、同年9月7日、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕し、同月9日、Qに送致した。Qは、同日、①H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
3 甲は、逮捕・勾留中、一貫して黙秘した。Pは、その間、甲の所持する携帯電話機や甲方から押収したパソコン等の解析、甲と交友関係にある者の取調べ、V方周辺の防犯カメラに映っていた不審者に関する更なる聞き込みなどの捜査をしたが、実行犯の氏名及び所在も前記腕時計が甲に渡った状況等も判明しなかった。
そのため、Qは、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲について公判請求するのは困難であると考え、勾留延長期間が満了する同月28日、甲を釈放した。
4 乙は、同年10月6日、別事件で逮捕され、その後の取調べにおいて、Pに対し、本件住居侵入・強盗致傷について、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行し、甲が換金する旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。
そして、Pが乙を逮捕した際に押収した乙の携帯電話機を解析したところ、本件住居侵入・強盗致傷について、甲との共謀を裏付けるメッセージのやりとりが記録されていることが分かった。
そのため、Pは、甲に対する嫌疑が高まったと考えて、同月19日、本件住居侵入・強盗致傷の事実につき、改めて逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕した上、同月21日、Qに送致した。そして、Qは、同日、②H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
〔設問1〕
下線部①につき、仮に検察官が本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行の事実を付加して甲の勾留を請求した場合、裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することができるかについて論じなさい。ただし、各事実につき、勾留の理由及び必要性はあるものとする。
〔設問2〕
下線部②につき、裁判官は甲を勾留することができるかについて論じなさい。
【出典:法務省ウェブサイト (●)】
解答例
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (●)】