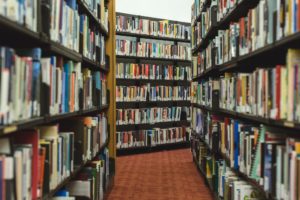【第17回】 後見の準拠法

…というわけなんです。
「理想の小説が書けた」という伯父(B)の作品を伯母(A)が読み始めたところ、その内容が支離滅裂で全く理解できず…
テーマ
1.国際裁判等管轄等
● 後見開始の審判の管轄
● 後見に関する審判の管轄
2.準拠法選択等
● 後見
3.外国判決等の承認・執行等
● 外国後見審判等の承認
事案
● 律子の伯父B(甲国人・日本居住・55歳)は、事理弁識能力を欠く常況にある。
● 律子の伯母A(日本人・日本居住・55歳)は、配偶者であるBの成年後見人となり、Bと日本で暮らして行きたいと考えている。
● そこで、Aは、日本の裁判所において、Bにつき後見開始の審判の請求をすることを検討している。

伯母さんとのお話には続きがあったのですね…
本事案も、日本・甲国に跨ることから、「国際的私法関係」に属しますね。これまでと同じく(広義の)国際私法の観点から考えて行きましょう。暫く前まで話題にしていた財産法分野に属する事項とは異なり、本事案のように「人事」・「家事」に関係する事項には、様々な特殊性があります。引き続き、その点に留意しながら進みましょう。
事案によれば、まず、通則法5条(後見開始の審判等)の問題となりますね。
1つ大切なことを。「後見」については、(民法同様)国際私法上も、未成年後見・任意後見契約等も問題となります。しかし、今回は、事案に即して個別的・具体的に検討する観点から、及び理解の便宜上(混乱の予防上)、原則として、成年後見に絞ってお話しますね。
1.国際裁判等管轄等

(1)成年後見開始の審判
(後見開始の審判等)
第五条 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
●趣旨(日本の「住所」・「居所」・「国籍」を国際裁判管轄の管轄原因とする趣旨)
・ 日本に住所・居所を有する者については、日本の裁判所による本人保護・取引の安全確保の必要性があること。また、事実関係調査も容易と考えられること。
・ 日本人については、場所を問わず(日本におけるか否かに関わらず世界中で)、本人保護の必要性があること。また、事実関係調査も可能と考えられること。等
● 主語・述語
「裁判所は…後見開始、保佐開始又は補助開始の審判…をすることができる。」と、その大枠において、国際裁判管轄について規定している(通則法5条)。
● 「後見『開始』…の審判」
行為能力を制限するための後見開始の審判
(なお、「保佐」・「補助」については、「後見」と同様に理解すれば足りることから、以下、「後見」に絞って解説。)
● 日本に住所・居所を有しない外国人(通則法5条では規定されていない「空白部分」)について
本人の具体的な状況の調査(後見の審判の前提として必要)の実施に限界があること等から、後見開始の審判については、日本の裁判所の国際裁判管轄は認められない。
(失踪宣告(通則法6条2項)と同様の例外条項は規定されていない。)

財産法分野については、通則法は大宗が準拠法(実体法)選択規則である、という前提でお話して来ましたので、通則法5条の話において「審判」という手続法的概念が明文で登場し、また国際裁判管轄の話にもなっている点等から、もしかすると困惑されているかもしれません。
ただ、現時点では、通則法5条は(6条も)例外である、という結論だけ念頭に置きつつ先に進みましょう。

そう言われても、依然として何か不思議な気持ちがしますが…
それはさておくと、日本居住の伯父(B)は(外国人(甲国人)ではあるものの)「日本に住所…を有する」ことから、後見開始の審判については、日本の裁判所の国際裁判管轄は認められると理解しました。

それでは次に、準拠法選択のフェーズに入りましょう。

…先程から不思議な気持ちがする理由が判りました。
今し方、通則法5条は(6条も)通則法の中では例外的に国際裁判管轄につき規定する旨のお話がありました。しかし、通則法5条にも、「日本法により」との文言があります。それは、あくまで準拠法選択規則ではないでしょうか?

まだ私の説明が不十分だったようですね…
通則法5条は(6条も)、国際裁判管轄につき規定するのと同時に、準拠法選択規則(通則法本来の規定)でもあるのです。
2.準拠法選択等

(1)成年後見開始
(後見開始の審判等)
第五条 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
● 趣旨(通則法5条が「日本法により」とする趣旨)
「後見開始の審判等は、裁判所による手続が必要なものであるため、そのための手続法と後見開始等の原因及び効力を規律する実体法とは密接な関係が有ること、審判地法をもって後見開始等の原因及び効力の準拠法とすることによって成年被後見人等の保護を実効的に行うことができるものと考えられたこと」(内野・一問一答 127頁)
● 単位法律関係
「後見開始」
後見開始の審判の要件(申立権者等)・効果(被後見人の行為の効力等)等
● 連結点
法廷地
● 準拠法
日本法

人事・家事の分野においては手続法と実体法が密接な関係にある点、民事訴訟法等で学習する「非訟事件」、或いは「形式的形成訴訟」(境界画定訴訟等)を想起しつつ、凡そのイメージは持つようにして下さい。

イメージと言えば…、伯母(A)は、後見開始の審判がされたとして「実際問題として、自分が日々『どう動けば良いのか』イメージできない」と言っていました。
(2)成年後見(原則)
(後見等)
第三十五条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
2 (略)
● 趣旨
本国法主義
【注意点】
・まず、同じ「後見」という文言の使用に関わらず、 「後見『開始』」(通則法5条)と「後見」(通則法35条1項)とは明確に区別する。
(「後見」(通則法35条1項)は、「後見開始」(通則法5条)を前提にした次の段階、即ち後見人の選任・権限・監督・解任等を指す。 )
・とはいえ、初学者には区別が難しい(イメージが持ち難い)。
少なくともその理由の1つは、「後見」(通則法35条1項)という一般的な(広い)概念が、「後見『開始』…の」(通則法5条)を包含するように読める等、通則法の文言のみからは両者の区別が読み取り難いことに起因するように思われる。
(国際私法を学ぶ前提として、内国法である民法(家族法)・家事法等をシッカリ学んでさえいれば…とは言えるが、当該分野の一般的な学習の実態・現実に照らすと非現実的な理想論(いわゆる「採点実感」的なもの)に過ぎない。)
・そこで、「明確に区別する」(理解する)ための具体的な方法は下記の通り。
1.イメージ
認知症に罹患した人が、福祉施設「成年後見」に入所し生活する場合、下記2つのプロセスを経る。
(1)申込み・入所決定・入所後の制約等の確認乃至設定(「後見『開始』…の審判」(通則法5条)に相当)
(2)担当者の選任・権限・監督・解任等に関する決定(「後見…に関する審判」(通則法35条1項)に相当)。
2.手元情報の活用
民法の条文の表題を「眺める」(特に学習が及んでいないと思われる(2)については、本文を含め、一度は一読することが有益ではある。)。
(1)7条以下の条文(「後見『開始』…の審判」(通則法5条)に対応)
(2)838条以下の条文(「後見…に関する審判」(通則法35条1項)に対応)
● 成年後見の国際裁判管轄(争いあり)【注意】便宜上、「2.準拠法選択等」において解説するものの、あくまで国際裁判管轄の問題。
・ 問題の所在:通則法35条1項は、純粋な準拠法選択規則(通則法の本来的な規定)であり、国際裁判管轄規定ではない。
(「日本法による」との文言はあるが、 「裁判所は…することができる。」等の文言が存在しない(通則法5条(・6条)参照)。
・ 解釈に委ねられているため、様々な説が存在するが、まずは全体像理解を優先させる便宜上、ここでは一旦、「住所・居所・財産等の存在を考慮要素としつつ、日本における要保護性を個別具体的に判断する」(根拠:条理)と理解しておく。
● 単位法律関係
「後見」
後見人の選任・権限・監督・解任等
● 連結点
国籍
● 準拠法
本国法

「5」・「35」なので、「5」つながりで、条文番号は覚えてしまったでしょう。と言っておけば、そうでなくとも記憶に残りますね(笑)。
内容面につき、通則法5条・35条1項の区別は良く理解しておいて下さい。

本事案において、叔父(B)は、(外国人(甲国人)ではあるものの)日本居住です。また、事理弁識能力を欠く常況にあることから、 日本における要保護性も認められます。よって、その後見人選任については、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められます(根拠:条理(上述))。
そして、準拠法選択レベルの話として、伯母(A)が伯父(B)の後見人に選任されるか否かについては、原則として、伯父(B)の本国法たる甲国法によることになるはずです(通則法35条1項)。
しかし、日本の裁判所において、日本法に基づき後見開始の審判がされたにも関わらず、後見人の選任等については叔父(B)の本国法(甲国法)による、という点、具体的にどのような顛末となるのか、イメージができません。

そこで、通則法35条には、2項柱書の下、(1号は一旦さておき)2号があります。
(3)成年後見(例外1)
(後見等)
第三十五条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
2 前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
一 (略)
二 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。
● 趣旨(「日本法による」(35条2項柱書))
外国人に対しても、日本法に基づく必要最小限の保護措置を行うことを可能にするため。
・日本に住所または居所を有する外国人に限定していない趣旨(かつて、法例24条2項においては、かかる限定が付されていた)
「…外国人の財産が日本に所在し, その処分の必要がある場合など, 我が国の裁判所が後見等の保護措置を行うことが必要となる場合が考えられることから」
・「後見」一般(通則法35条1項)ではなく、「後見等に関する審判」に限定した趣旨
「原則としての本国法の規律を尊重する」ため。
【小出・一問一答 144頁参照】
【注意点】
・まず、前述の通り、同じ「後見」という文言の使用に関わらず、 「後見『開始』」(通則法5条)と「後見」(通則法35条1項)とは明確に区別する。
(「後見」(通則法35条1項)は、「後見開始」(通則法5条)を前提にした次の段階、即ち後見人の選任・権限・監督・解任等を指す。 )
・次に、「審判」という文言が付加的に使用されていることから、「後見…に関する審判」(通則法35条2項)は、「後見」(通則法35条1項)一般と比較し、より限定された事項について規定している点(上記趣旨参照)を理解する。即ち、後見人の選任・権限・監督・解任等に関する審判に限った規定であることを理解する。
(なお、通則法35条1項>2項の部分(1項独自の単位法律関係)としては、例えば未成年者に関する後見開始の原因(成年後見とは異なり、審判がなくとも、親権者がいないために後見が開始する等)が挙げられる。ただし、成年後見に絞って検討をする限り、その点は(35条1項・2項の「守備範囲」の広狭は)、一旦捨象しておいて良い。)
・上記からの当然の帰結として、同じ「審判」という文言の使用に関わらず、「後見『開始』…の審判」(通則法5条)と「後見…に関する審判」(通則法35条2項)とは明確に区別される。
(「後見」(通則法35条2項)に関する審判は、後見「開始」を前提にした次の段階、即ち後見人の選任・権限・監督・解任等に関する審判を指す。)
● 成年後見の国際裁判管轄(争いあり)【注意】便宜上、「2.準拠法選択等」において解説するものの、あくまで国際裁判管轄の問題。
・ 前述の通則法35条1項と同様。理解の便宜上、2項について、重ねて下記しておく。
・ 問題の所在:通則法35条2項は、純粋な準拠法選択規則(通則法の本来的な規定)であり、国際裁判管轄規定ではない。
(「日本法による」との文言はあるが、 「裁判所は…することができる。」等の文言が存在しない(通則法5条(・6条)参照)。
・ 解釈に委ねられているため、様々な説が存在するが、まずは全体像理解を優先させる便宜上、ここでは一旦、「住所・居所・財産等の存在を考慮要素としつつ、日本における要保護性を個別具体的に判断する」(根拠:条理)と理解しておく。
● 単位法律関係
「後見…に関する審判」
後見人の選任・権限・監督・解任等に関する審判
● 連結点
法廷地
● 準拠法
日本法

本事案においては、伯父(B)が日本で後見開始の審判を受けることになりますので、伯母(A)の後見人としての選任・権限等については、日本法(民法838条以下)によることになるのですね(通則法35条2項2号)。

もうひとつの例外である通則法35条2項1号については、便宜上、後ほど解説しますね。
3.外国判決等の承認・執行等

【設例1】
● 律子の伯父B(甲国人・日本居住・55歳)は、事理弁識能力を欠く常況にある。
● 律子の伯母A(日本人・日本居住・55歳)は、配偶者であるBの成年後見人となり、近くBと甲国で暮らして行きたいと考えている。
● そこで、早目に準備を進めようと考えたAは、甲国の裁判所において、Bにつき後見開始の申立てをし、(甲国法上、その原因が存在するとの理由により)それが認められた。しかし、現地でのAの就職・引越し準備等がままならず、当面、引き続き日本で生活して行くこととなった。

ここでは、1つ新しい問題意識を獲得して下さい。
それは、外国裁判所等による成年後見開始の審判等については、(承認要件吟味の前に)そもそも承認対象とすべきではないのでは?、という点です。
(1)外国成年後見開始の審判の承認
● 問題の所在
外国裁判所等による成年後見「開始」の審判等については、日本における登記がされないため、日本における取引の安全を害するのではないか?
・承認否定説(通説)
・承認肯定説
この説によった場合、家事事件についての裁判の承認に関する規定(家事法79条の2・民訴法118条)の適用の有無、及び(適用される場合の)解釈が問題となる。
● 外国における成年後見人「選任」の審判の承認も問題となりえるが、ここでは立ち入らない。

ここでは、便宜上、通説によることとしましょう。

そうすると、設例1の場合、甲国における後見開始の審判は日本における承認対象とはされないため、伯父(B)は成年被後見人としての保護を受けられないまま、当面日本において生活して行かざるをえないのですね…

それでは、ここで先程言及したもう1つの例外(通則法35条2項1号)について解説しますね。
ただし、解説・理解の便宜上ここで触れるだけですので、あくまで性質上は「準拠法選択」の問題である点は、認識しておいて下さい。
4.補足
(1)成年後見(例外2)
【設例2】
● (上記設例1において)その後、律子の伯母(A)は、勤務先企業の転勤命令により日本を離れ、乙国で働かざるを得なくなった。
(後見等)
第三十五条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
2 前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
一 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
二 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。
● 趣旨
(「日本法による」(通則法35条2項柱書))
外国人に対しても、日本法に基づく必要最小限の保護措置を行うことを可能にするため。

伯父さん(B)は、本国たる甲国においては成年後見開始の審判まで受けているので、「当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合」に該当します。
そして、伯母さん(A)が乙国に働きに行くことになれば、「日本における後見等の事務を行う者がない」こととなりますので、「日本法」により、日本において伯父さん(B)の後見人(例えば律子さん)が選任される可能性がありますね(通則法35条2項1号)。
なお、念のため繰り返しお伝えしておきますが、この点は、準拠法選択の問題です。

もし架空の「設例」でなければ、早速伯母(A)に連絡をし私が後見人になり…はい、律子です。あっ、伯母さんですか!…はい…えっ!?…そうなんですか…

再び伯母さんからお電話ですね…。
では、その間に、成年後見との比較で、未成年後見につき、要点のみホワイト・ボードに板書しておきましょう。
(2)未成年後見(補足)
● イメージ
自己に対し(管理権を伴う)親権を行使する者が存在しない未成年者が、 福祉施設「未成年後見」に入所し生活する場合、下記2つのプロセスを経る。
(1)(入所決定がなくとも自動的に)入所することとなる(「後見」の準拠法(通則法35条1項)上の後見開始の原因に相当)。
(2)それとは別に、具体的な担当者の選任・権限・監督・解任等に関する決定
(「外国人」の場合、「後見…に関する審判」(通則法35条2項柱書)に相当。日本人の場合、「外国人」に関する例外規定である2項ではなく、(2項より規定範囲が広い)通則法35条1項に包含される。)
家事事件手続法
(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)
第三条の九 裁判所は、養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。第百七十六条及び第百七十七条第一号において同じ。)又は未成年後見人の選任の審判事件(同表の七十一の項の事項についての審判事件をいう。同条第二号において同じ。)について、未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。
1.国際裁判等管轄等
(「成年被後見人」との形式文言、及び実質的にも未成年後見は審判を待たず(親権を行う者がいない場合等に補充的に)開始されることから、未成年後見は通則法5条とは無関係。)
・ 後見開始・後見人の選任等のいずれについても、通則法に規定なし。
・ 未成年後見人の選任に関する国際裁判管轄(家事法3条の9)
未成年被後見人の住所・居所・国籍を管轄原因として、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められている。管轄原因は通則法5条と同様。
2.準拠法選択等
(「成年被後見人」との形式文言、及び実質的にも未成年後見は審判を待たず(親権を行う者がいない場合等に補充的に)開始されることから、未成年後見は通則法5条とは無関係。)
・ 通則法35条1項
単位法律関係として、「後見開始の原因」(未成年者については、親権者がいないこと)・後見人の選任・権限・解任等が挙げられる。
(なお、前述の通り、通則法35条1項は、日本人の成年後見(審判)についても適用される。その場合の「後見開始の原因」は、後見開始の審判があったこと。「後見開始の原因」(通則法35条1項の「後見」に含まれる単位法律関係)と「後見開始の審判の原因」(通則法5条の「後見開始の審判」に含まれる単位法律関係)も峻別する。)
・ 通則法35条2項1号
(未成年者については、通則法35条2項2号(「後見開始の審判等」)は無関係。前述の通り、未成年後見については、親権者がいないこと等が「後見開始の原因」であり、後見開始の審判が要件ではないため。なお、当然のことながら、通則法35条2項1号が、成年後見に適用されない訳ではない。)
3.外国判決等の承認・執行等
・ 家事法79条の2・民訴法118条
まとめ
1.国際裁判等管轄等
● 通則法5条
● 家事法3条の9
● 条理
2.準拠法選択等
● 通則法5条
● 通則法35条1項
● 通則法35条2項1号・2号
3.外国判決等の承認・執行等
● 人訴法79条の2
● 民訴法118条
4.補足
● 家事法3条の9
● 家事法79条の2・民訴法118条

…丁度伯母(A)から電話があり、伯父(B)の小説の内容が支離滅裂で理解できないというのは伯母(A)の誤解だったようです…。念のため知り合いの小説家に見せたところ、ある文学賞に応募してみては、と奨められたそうです!

そうでしたか。
応募自体(形式面)は自由ですし、公式に「支離滅裂」と評価されるリスクをテイクすること(実質面)も自由です。
反対しても致し方ない、かと。
最後に、甲国法等の外国法への向き合い方については、こちらを参照しておいて下さい。
●「外国法(向き合い方)~準拠法として」

反対しても致し方、といえば…
【第18回】 相続の準拠法