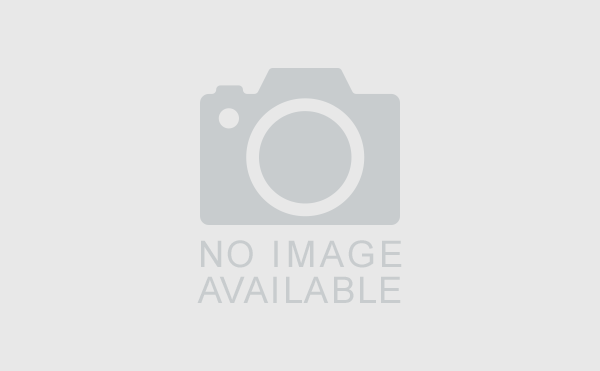【第16回】 失踪宣告の準拠法

…というわけなんです。
伯父(B)は小説家を志すと言いつつ気儘な生活をしていたため、伯母(A)としては、最近は離婚まで考えていたようですが…
テーマ
1.国際裁判等管轄等
● 失踪宣告の管轄
2.準拠法選択等
● 失踪宣告
3.外国判決等の承認・執行等
● 外国失踪宣告の承認
事案
● 律子の伯母A(日本人)は、日本で生まれ育ったものの、甲国で生まれ育ったB(甲国人・甲国居住)と婚姻して以降、甲国において暮らしていた。
● ところが、ある日突然Bが行方不明となり、その後4年が経過したため、Aは日本に帰国し、現在一人で暮らしている。
● その後4年(合計8年)経過してもBは行方不明のままであったため、Aは、友人C(日本人・日本居住)との再婚を考え、日本の裁判所において、Bにつき失踪宣告の請求をした。

そうですか…
本事案も、日本・甲国に跨ることから、「国際的私法関係」に属しますね。これまでと同じく(広義の)国際私法の観点から考えて行きましょう。
ただし、先程までの財産法分野に属する事項とは異なり、本事案のように「人事」・「家事」に関係する事項には、様々な特殊性があります。その点に留意しながら進みましょう。

…そういえば、伯父(B)は、勤務先の会社で「尊敬できる上司だった課長が異動になって困った」、或いは家では「風呂掃除をサボって伯母に怒られた」等の話をしていました…。もしかして、それが原因で…

…(色々)残念です…
現時点では、「人事」は伯母さんが考えていた離婚に関する訴訟等、「家事」は今回お話する失踪宣告等を含む法的概念、とのみ認識しておいて下さい。詳しくは、人事訴訟法・家事事件手続法に規定がありますが。
なお、「人事」・「家事」については、その性質上、国家により法制度化されている点も多く、「財産法」と比較すると、テーマにバリエーションはありません(例えば、当事者自治の原則に基づく多種多様な契約等との比較)。そのため、ある意味「シンプル」ではあります。
しかし、真に理解しようとすると、内国法に限っても、民法(家族法等)は勿論のこと、前述した人事訴訟法(及び人事訴訟規則)・家事事件手続法(及び家事事件手続規則)、更に国籍法・戸籍法(戸籍実務)等まで、広く深く学ばなければなりません。ただ、現時点では、要点を絞り、お話します。
1.国際裁判等管轄等

(1)留意点(人事・家事)
● 管轄
家事・人事に関しては、裁判所・行政機関が広く関与するため、財産法分野とは異なった観点から、それら公的機関の管轄・実務が問題となる。
・裁判所の後見的機能(訴訟等の処理ではない)、及びそれを果たすための管轄・実務が問題となる。
・戸籍法に基づく「戸籍実務」が問題となるが、その点、法務大臣・市町村長等(行政機関)が所管する。
(戸籍実務における考え方を理解することで、国際私法(人事・家事分野)の理解が深まる。)
● 条文
条約・特別法にも規定が置かれている他、下記条文が置かれている。
・ 人事訴訟法(「人訴法」)
「第二節 裁判所」→「第一款 日本の裁判所の管轄権」(3条の2~3条の4)
・ 家事事件手続法(「家事法」)
「第一章の二 日本の裁判所の管轄権」(3条の2~3条の13)
・ 通則法5条(後見開始の審判等)・6条(失踪の宣告)
【注意】
・通則法は、原則として「準拠法選択」に関する法律であるが、上記2条項(通則法5条・6条)については、例外(その背景等は別途解説)。
・国際裁判管轄に関する条項として、民事訴訟法3条の2以下同様、「住所」概念を使用(準拠法選択上の連結点たる「常居所」は使用せず)。
【留意点】
本国管轄
・ 人事・家事分野においては、財産分野とは異なり、国籍を管轄原因とすることがある(本国管轄)。
・ これは、人事・家事分野においては、国家が個人を後見的に保護する側面があること、及び国家としても(その構成員として必要最小限)個人の人事・家事につき把握等する側面があること等に基づく。
・ 本国管轄については、財産分野の管轄原因と比較し非常に特徴的な管轄原因であるにも関わらず、(1)その存在・趣旨は所与の前提として、住所地・居所地管轄との比較に重点が置かれるのが一般的であること(実質面)、及び(2)通常は最初に学ぶ民事訴訟法の条文において、「国籍」との文言が1つも存在しないこと(管轄原因としては、人訴法・家事法まで学んで初めて登場すること)(形式面)等から、その意義・重要性自体を独立して学習する機会が不足している(※)ように思われる。そのため、その趣旨・重要性等につき考える端緒とすべく、ここで明示的に注意喚起をしておきたい。
(※)準拠法選択のテキストブック「総論」においては、本国法主義・住所地法主義の対比について解説されるのが一般的である。そのことと比較し、大きく異なる。その理由と考えられるところは、ここでは立ち入らない。
(2)失踪宣告(原則的管轄)
(失踪の宣告)
第六条 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
2 (略)
●趣旨(日本の「住所」・「国籍」を国際裁判管轄の管轄原因とする趣旨)
・ 日本に住所を有していた者については、相当数の利害関係人が日本に所在しているであろうこと。
・ 日本人については、その生死という重要な身分関係事項を戸籍に反映する必要性が高いこと。等
● 主語・述語
「裁判所は…失踪の宣告をすることができる。」と、その大枠において、国際裁判管轄について規定している(通則法6条1項)。

財産法分野については、通則法は大宗が準拠法選択規則である、という前提でお話して来ましたので、混乱しているかもしれません。
ただ、現時点では、通則法6条は(5条も)例外である(その大宗が準拠法選択規則である通則法において)、という結論だけ念頭に置きつつ先に進みましょう。

そう言われても、依然として何か不思議な気持ちがしますが…
それはさておくと、伯父(B)は甲国で生まれ育った甲国人(甲国居住)であることから、通則法6条1項における「住所」も「国籍」も日本には無く、日本の裁判所の国際裁判管轄は認められないと理解しました。
通則法6条には2項もあるようですが、どのような内容なのでしょうか?
(3)失踪宣告(例外的管轄)
(失踪の宣告)
第六条 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
2 前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
●趣旨(通則法6条2項が例外的管轄を認める一方、「のみ」と制限をする趣旨)
下記2点の調和の観点から、日本に住所がない外国人について、日本の裁判所による失踪宣告を限定的に可能とする趣旨。
・ 日本における財産、及び日本に関係がある法律関係について、法的安定性を確保する必要性
・ 日本における失踪宣告が外国に与えうる影響を最小限に抑える必要性(国際協調主義)
● 主語・述語
「裁判所は…失踪の宣告をすることができる。」と、その大枠において、裁判管轄について規定している(通則法6条2項)。
● 適用範囲
(通則法6条1項)
「日本に住所がない外国人」以外の者、即ち(1)日本人、及び(2)日本に住所がある外国人については、通則法6条1項がカバー。
● 「のみ」
(通則法6条2項)
仮に「のみ」との限定文言がないとしても、日本の裁判所により「日本に住所がない外国人」につきされた失踪宣告(無限定)を外国が承認さえしなければ、結局、当該外国には日本の裁判所による失踪宣告の効力は及ばない。しかし、そのようなプロセスを経ることなく、当初から必要性に照らした最小限の効力に限定する(国際協調主義)、というのが通則法6条2項の趣旨だと理解できる。

本事案において、伯母さん(A)は、日本で生まれ育った日本人であり、かつ現在は帰国して日本に住んでおり、更には(Bとの婚姻関係を終了させ)Cさん(日本人・日本居住)と婚姻しようとしているのですから、少なくとも「不在者に関する法律関係」が「日本に関係があるとき」(通則法6条2項)には該当するでしょう。
したがって、本事案においては、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められます。

…先程から不思議な気持ちがする理由が判りました。
少し前に、原則として準拠法選択規則である通則法においても、通則法6条は(5条も)例外的に国際裁判管轄につき規定する旨のお話がありました。しかし、通則法6条の1項にも2項にも、「日本法により」との文言があります。それは準拠法選択規則ではないでしょうか?

私の説明が不十分だったようですね…
通則法6条は(5条も)、国際裁判管轄につき規定するのと同時に、準拠法選択規則(通則法本来の規定)でもあるのです。
2.準拠法選択等

(1)失踪宣告
(失踪の宣告)
第六条 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
2 前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
● 趣旨(通則法6条1項・2項が「日本法により」とする趣旨)
「失踪の宣告は裁判所が後見的な判断を行うものであって裁判所による手続が必要であると考えられ、このような場合には審判地以外の準拠法の適用は困難と考えられたことによる」(内野・一問一答 93頁)。
【補足】
(「日本法によるべきとき」)【注意】便宜上、「2.準拠法選択等」において解説するものの、あくまで国際裁判管轄の問題。
● この文言は、前述した「日本法により」とは異なり、問題となっている法律関係の準拠法が日本法である場合、を意味している。
● 具体的には、「日本法により」は、前述の通り「失踪宣告の準拠法」の問題であるのに対し、「日本法によるべきとき」は、あくまで国際裁判管轄の問題として、「日本法が準拠法となる法律関係については、日本の裁判所の国際裁判管轄を認める」趣旨の文言。
(例えば、失踪宣告(死亡擬制)により法的安定性を確保すべき法律関係として、「保険契約」・「婚姻関係」等の準拠法が想定される。)
● なお、(「日本法によるべきとき」に続けて)「その他」と規定されているのは、たとえ日本法が準拠法となる場合でなくとも、「日本に関係があるとき」でさえあれば、広く日本の裁判所の国際裁判管轄を認める趣旨。

本事案において、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められること、即ち「日本法」が適用されることになります(通則法6条2項)。
その結果、8年間行方不明の伯父さん(B)については、失踪宣告がされることになりそうですね(民法30条1項)。もしそうなれば、伯父さん(B)は、行方不明になってから7年間が満了した時に死亡したものとみなされます(民法31条前段)。
もっとも、一般的には、失踪宣告の準拠法の適用範囲は、そのような死亡擬制という直接的効果に限定されます。
したがって、当該直接的効果を前提として、死亡により婚姻関係が解消されるか否かという間接的な効果については、別途準拠法が検討されることとなります。
その結果次第では、伯父さん(B)が失踪してから8年間が経過した現在であっても、伯母さん(A)がCさんと婚姻した場合に重婚となるか否かは不明ですね。ここでは、その検討は割愛しますが。

「Cさんと婚姻」と言えば…、伯母(A)は、伯父(B)がどこかで生きているのではないかと、Cさんとの再婚についてはまだ迷っているようなのです。仮に伯父(B)が不意に伯母(A)のところに帰って来た場合、既に下された失踪宣告はどうなるのでしょう?通則法には明文がないようですが。
(2)失踪宣告の取消し
【設例】
● (本事案において失踪宣告が下された後)行方不明だったBが、Aの前に現れた。
● Bは、日本の裁判所において、失踪宣告の取消しを請求しようとしている。
家事事件手続法
(失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
第三条の三 裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
一 日本において失踪の宣告の審判があったとき。
二 失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。
三 失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。
● 趣旨
(家事法3条の3第1号)
「失踪の宣告をした裁判所がこれを是正することが相当」であるため(内野・一問一答 92頁)。
● 趣旨
(家事法3条の3第2号・3号)
「外国裁判所が行った失踪の宣告についても、わが国においてその効力が認められるものがあり得ると考えられるため…必要が生じる」から(内野・一問一答 92頁)。
● 失踪宣告の取消しの国際裁判管轄
失踪宣告(通則法6条2項)同様の例外的な管轄原因は認められていない。その必要性が無いため、と一般に説明されている。
【注意】念のため、「2.準拠法選択等」において解説するものの、あくまで国際裁判管轄の問題。
● 「失踪宣告の取消し」の準拠法
・明文なし。
・日本の裁判所における手続と密接に関連することから、日本法(民法32条)によると一般に解されている。

本設例は、日本の裁判所による失踪宣告がされた場合の話ですから、その取消しについても日本の裁判所の国際裁判管轄が認められますね(家事法3条の3第1号)。

???
先程「1.国際裁判等管轄等」は終えた後にも関わらず、先程の「日本法によるべきとき」(通則法6条2項)という国際裁判管轄の話に続け、更に国際裁判管轄の話が出てきましたね…

裁判所・行政機関が関与して成立等した法律関係等について、その無効・取消し等が問題となる場合、再び管轄が問題となる場合は勿論ありますからね。
前後しましたが、その話の前提として、国際裁判管轄・準拠法選択の関係性について、そもそも国際私法(人事・家事分野)を学ぶに際し留意しておいた方が良いことを簡単に述べておきます。
(3)留意点(人事・家事)
● 国際裁判等管轄と準拠法選択との混在
1.「日本の裁判所の国際裁判等管轄が認められるので、日本法が準拠法となる」等の考え方が強く現れる場合あり。財産法分野との対比。
(例:「日本法により」(通則法6条1項・2項))
2.「日本法が準拠法なので、日本の裁判所の国際裁判等管轄が認められる」等の考え方が強く現れる場合あり。財産法分野との対比。
(例:「日本法によるべきとき…失踪の宣告をすることができる。」(通則法6条2項))
しかし、人事・家事分野においても、両概念(国際裁判等管轄と準拠法選択)は明確に区別する必要がある。むしろ、財産法分野よりも両者の区別を明確に意識して学習する必要性が高い。

一見複雑そうですが、国際裁判等管轄と準拠法選択とが密接に関係するのであれば、一緒に話をして頂いた方が、理解・効率の両面でベターに思われます。

今後も、失踪宣告の取消しの解説同様、実質面については「国際裁判等管轄」・「準拠法選択」のいずれの議論であるかは明示しつつも、形式面については、お話する箇所が「1.国際裁判等管轄等」か、「2.準拠法選択等」かには拘泥せず、柔軟に対応したいと考えています。
(なお、通則法6条については(5条についても)、手続と準拠法との密接関連性に照らし、敢て法例以来の規定形式(国際裁判管轄・準拠法双方に関する規定が混在)を維持したようです。)
以上の次第ですが、民法において財産法分野の学習が中心であることも相俟って、現時点で簡単に理解できるとは考えていません。もし引き続き国際私法を学ぶのであれば、人事・家事分野の特殊性につき徐々に慣れて行って頂きたいところです。
3.外国判決等の承認・執行等

(1)留意点(人事・家事)
家事事件手続法
(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)
第七十九条の二 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。
● 趣旨
(「その性質に反しない限り」(人訴法79条の2))
家事分野においては、訴訟事件・それに類して対立当事者が存在する家事事件の他、「対立当事者の存在が前提とされておらず国が後見的に関与をする事件もあるなど、多様な事件の性質に応じた柔軟な承認要件の設定を許容する必要」があるため(内野・一問一答 159頁)。
民事訴訟法
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
【財産法分野との比較】
● 「確定判決」(民訴法118条柱書)
外国「判決」(及び、その他の裁判(決定・命令))の他、外国における審判・調停等に相当する手続等も問題となる。
● 「裁判権」(民訴法118条1号)
・外国の裁判所・行政機関も関与するため、管轄(裁判管轄に限らず)が問題となる。ただし、間接管轄の問題として。
・解説の便宜上、人事・家事分野においても、「鏡像理論」を採用(ただし、特に人事・家事分野につき、反対説があることは要復習)。
【参考】「行為能力の準拠法(1)」→「3.外国判決の承認・執行」→「(2)判断基準」
● 「被告」(民訴法118条2号)
「被告」が存在しない事件(失踪宣告等)については、「その性質」(家事法79条の2)に反するため、民訴法118条2号は準用されないと一般に解されている。
● 「公の秩序又は善良の風俗」(民訴法118条3号)
公序に反するか否かは、(財産法分野と異なる)人事・家事分野における各国法の「多様性」を勘案しつつ、相当程度慎重に決せられるべき。
(なお、公序に反するか否かは、(人事・家事分野とは異なる)財産法分野における各国法の「類似性」を勘案しつつ、相当程度慎重に決せられるべき。とも言えるが。これ以上立ち入らない。)
● 「相互の保証」(民訴法118条4号)
相互の保証については、財産法分野か家事・人事分野かを問わず、少なくとも立法論的に問題があるという点において大きな争いはない。
【留意点】
内国判決等の承認・執行
・ 人事・家事分野においては、財産法分野とは異なり、「内国判決等が外国において承認等されうるか?」という観点が非常に重要となる。
・ これは、人事・家事分野においては、どこの国においても同様の身分・家族関係が認められることが望ましい、という価値判断に基づく。
・ 国際私法の学習の観点から「外国判決等の承認・執行」と比較すると、(1)上記観点(「普段」とは「逆」の発想)が求められること(実質面)、及び(2)独立した学習項目とはならないことが通常であること(形式面)から、左程意識されていないと思われる機会も多いため、ここで敢て強調しておく。
(なお、(2)について、「独立した学習項目」とすることは、即ち「外国国際私法(民事訴訟法等)の学習」を意味する。事実上困難。)
(2)外国失踪宣告の承認
【設例】
● 律子の伯母A(日本人)は、日本で生まれ育ったものの、甲国で生まれ育ったB(甲国人・甲国居住)と婚姻して以降、甲国において暮らしていた。
● ところが、ある日突然Bが行方不明となり、8年経過しても音信不通であるため、Aは、甲国の裁判所において、Bにつき失踪宣告を得た。
● その後、Aは、ネットで知り合った友人D(日本人・日本居住)と結婚するため、日本に帰国し、現在はDと暮らしている。

本設例においては、特段の問題点はなさそうですので、甲国裁判所による失踪宣告は日本で承認されるでしょう。そして、当該失踪宣告の具体的効果(直接的効果か、間接的効果か)次第ではありますが、伯母さん(A)はDさんと再婚できる可能性がありますね。

今回は、財産法分野に慣れきった頭で人事・家事分野のお話を聞いたため、なかなか理解が深まるにまでは至りませんでした。しかし、凡そのイメージは持てたため、もし国際私法を学ぶのであれば、なんとかやっていけそうな気が…はい、律子です。あっ、伯母さんですか!…はい…えっ!?…そうなんですか…ではまた…
まとめ
1.国際裁判等管轄等
● 通則法6条1項・2項
● 家事法3条の3
2.準拠法選択等
● 通則法6条1項・2項
3.外国判決等の承認・執行等
● 人訴法79条の2
● 民訴法118条2号

…失礼しました。今、伯母から電話があり、伯父が「やっと理想の小説が書けた」と言いながら、戻って来たらしいです。もはや私の想像力の域を超えますが、Cさんとは別れ、再び伯父と結婚生活を続けることにしたらしいです。というのも…

…まぁ、伯母さんの人生の選択ですから。伯母さんも、ある意味で、伯父さんがいなければやって行けない面があった、ということではないでしょうか。
最後に、甲国法等の外国法への向き合い方については、こちらを参照しておいて下さい。
●「外国法(向き合い方)~準拠法として」

いなければやって行けない、といえば…
【第17回】 後見の準拠法