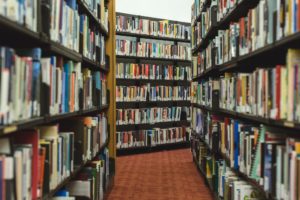【第15回】 法人の準拠法

…いうわけなんです。
請求の目的物であるスーツケースの所在も良く判らないらしいのですが…
テーマ
1.国際裁判管轄
● 法人(会社等)等に関する訴え
2.準拠法選択
● 法人の準拠法
3.外国判決の承認・執行
● 間接管轄(専属管轄)
事案
● 律子の父が経営するR社(日本法人。主たる営業所所在地は日本。外国に営業所等を有しない。)は、ビジネス用品の製造・販売業者A社(甲国法人。主たる営業所所在地は乙国(★)。日本に従たる営業所(★)を有する。)の代表取締役(★)Bとの間で、日本において、スーツケース10,000個(「本件スーツケース」)の売買契約(準拠法:乙国法)(「本件売買契」)を締結し、Bに対し、現金5億円を手渡した。
● A社は、従たる営業所(日本所在)を通じ、ビジネス用品の販売事業・レンタル事業等(日本において)を営んでいる。
● A社は、Bとの委任契約(準拠法:甲国法)(「本件委任契約」)を締結したものの、A社におけるBの権限は、内規によりレンタル事業上のものに制限されており、売買に関する権限は有していなかった。他方、Bが売買に関する権限を有すると信じるにつき、R社に重過失(★)はなかった。なお、Bは、受領した5億円と共に行方不明となっている。
● 各国の法(会社法等)によると、代表取締役の権限に加えた制限について、会社が第三者に対抗しうるか否か等の結論については下記の通り。
・ 甲国法:「代表取締役の権限に加えた制限は、善意無過失の第三者に対抗することができない。」
・ 乙国法:不明(R社の法務担当者は、その点について調査した上で準拠法条項をドラフトした訳ではなかった)
・ 日本法:「前項(※1)の権限に加えた制限は、善意(※2)の第三者に対抗することができない。」(会社法349条5項)
(※1)「代表取締役は,株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」(会社法349条4項)
(※2)「善意」は「善意かつ無重過失」と一般に解されている。
● R社は、日本の裁判所において、A社に対し、本件売買契約が有効であることを前提に、本件スーツケースの引渡請求の訴えを提起した。

…お父さんの会社は同じような事件に何度も巻き込まれていますね…
先程お話した「代理の準拠法」における事案と比較すると、「★」印が付されている下記4点が異なりますね。
・A社の「主たる営業所」は乙国(甲国ではない)に所在。
・A社の「従たる営業所」が日本に所在(乙国に主たる営業所が存在するだけではない)。
・Bは「代表取締役」である(単なる代理人ではない)。
・R社には「軽過失」あり(重過失まではなかった)。
これまでと同様、広義の国際私法の観点で分析を加えてみましょう。
1.国際裁判管轄

(1)主たる営業所等所在地
(被告の住所等による管轄権)
第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

A社の主たる営業所は日本にはない(乙国にある)ため、この民訴法3条の2第3項に基づく国際裁判管轄は認められません。

その通りです。
(2)営業所等所在地
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
(略)
四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
(略)
● 趣旨
「業務の中心となっている事務所又は営業所は、その業務については住所に準ずるもの(業務の本拠地)とみることができ、証拠の収集という観点からも、その所在地のある国の裁判所に当該業務に関する紛争を審理させることが便宜」(佐藤=小林・一問一答 51頁)。
●「事務所又は営業所を有する者」は、法人に限定される。
●「事務所」は非営利法人の、「営業所」は営利法人(会社等)の業務遂行場所を指す。

「A社は、日本における従たる営業所を通じ、日本においてビジネス用品の販売事業・レンタル事業等を営んでいる。」ことから、A社は「営業所を有する者」に該当し、その「営業所が日本国内」にあります。
そして、父の会社(R社)による訴えは、A社製造の本件スーツケースの売買、即ちA社の「業務に関するもの」に係る訴えに該当します。
よって、本事案においては、この民訴法3条の3第4号に基づき、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められます。

その通りです。
(3)社団等に関する訴え
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
(略)
七 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
(略)
● 趣旨
・法人の場合
(設立準拠法国を国際裁判管轄の基準とする趣旨)
「その活動を規律する…基準とすることが相当」
・法人でない場合
(主たる事務所又は営業所の所在地国を基準とする趣旨)
「 法令により設立されるものではなく、様々な形態のものがあることから…基準とするのが相当」
【佐藤=小林・一問一答 66頁】
【整理】一読すればOK
民訴法3条の3第7号
● 訴えの類型(原告 → 被告)
イ. 社員としての資格に基づく訴え
・ 社団 → 社員・元社員
・ 社員 → 社員・元社員
・ 元社員 → 社員
ロ. 役員としての資格に基づく訴え
・ 社団・財団 → 役員・元役員
ハ. 発起人・検査役としての資格に基づく訴え
・ 会社 → 発起人・元発起人・検査役・元検査役
ニ. 社員としての資格に基づく訴え
・ 社団債権者 → 社員・元社員
● 管轄原因
・ 法人の場合: 日本の法令により設立されたものであるとき
・ 法人でない場合: 主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき

本事案には関係ありませんが、「法人」に関係する条文として一読の上、この機会に整理してみました。

それで結構です。

本事案においては、代表取締役の権限に加えた制限について会社が第三者に対抗しうるか否か等について、関係各国の法に違いがありますので、次に準拠法選択が問題となります。
2.準拠法選択

(1)法人の準拠法(概説)
● 法人の準拠法
・ 通則法上、明文なし。条理等による。
(2)法人の従属法
● 従属法
・ 同じく「人」である自然人の「属人法」同様、法人については「従属法」概念が存在し、その適用範囲につき議論がある。
● 単位法律関係(例)
・ 設立
・ 法人格(権利能力の存否・範囲・制限(後述))
・ 内部関係(機関等)
・ 外部関係(行為能力の存否・範囲・制限(後述))
・ 解散
● 連結点・準拠法(従属法)
代表的な考え方として、下記2つの説が存在する。
1.設立準拠法説
【メリット】
・ 安定性
・ 明確性(例:登記等)
【デメリット】
・ 法の潜脱(例:いわゆるペーパー・カンパニー)
2.本拠地法説
【メリット】
・ 実態に沿う
【デメリット】
・ 不安定(例:法人の任意による本社移転等)
・ 不明確(例:定款上の本店か、事実上の本店か等)

少なくともイメージとしては、「従属法」は自然人における「属人法」のようなもの、だと認識しました。また、「設立準拠法」は「本国法」のようなもの、更に「本拠地法」は「住所地法」のようなもの、と認識しました。

現時点における凡そのイメージは、それで結構です。
通則法上、属人法につき「本国法」主義が採用されていることとの類比で、少なくともここでは、「設立準拠法説」が有力な考え方であると理解しておいて結構です。

本事案に即して言えば、A社は「甲国法人」なので、設立準拠法は甲国法と認められ、それがA社の従属法ということですね。他方、主たる営業所所在地法である乙国法は従属法ではない、と理解しました。
(3)法人の権利能力
(人の行為能力)
第四条 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3 (略)
● 原則
・ 従属法が適用される。
● 例外
・ 通則法4条2項類推適用(有力説)
【理由】
行為地における取引の安全への配慮

①自然人の、しかも②行為能力に関する4条2項が、①法人の②権利能力につき類推適用されるとは、どういうことでしょうか?

通則法4条においては、本国法が原則的準拠法とされている(同条1項)一方、行為地における取引の安全への配慮(国際私法上)から、一定の要件の下、行為地法が例外的準拠法とされています(同条2項)。
それと同様、例えば会社の代表取締役が法人の定款の目的範囲外の行為を行った場合、法人の従属法(設立準拠法)によれば当該会社の権利能力が否定されているとしても、行為地法によれば肯定されるのであれば、行為地における取引の安全確保の必要性があります。
そのような利益状況と規定内容との類似性があることから、通則法4条2項は、法人の権利能力についても類推適用されるべき、という考え方があるのです。
ただ、本事案においては、A社の定款の目的等に関する留意点はなく、直接関係することはなさそうです。
(4)法人の行為能力
(人の行為能力)
第四条 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3 (略)
● 原則
・ 従属法が適用される。
● 例外
・ 通則法4条2項類推適用(有力説)
【理由】
行為地における取引の安全への配慮

行為能力についての解説ではあるものの、内容は権利能力に関するものと同様、と理解しました。

それで結構です。
ここでの話は(権利能力ではなく)「行為能力」の話ですので、文言上尚更4条2項(「行為能力」)が類推適用される素地がある、と言えるのかも知れませんね。

本事案に即して言えば、Bの代表権限は、原則としてA社の従属法(設立準拠法)である甲国法によることから、A「代表取締役の権限に加えた制限は、善意無過失の第三者に対抗することができない。」こととなります。そして、父の会社(R社)には軽過失が存在するため、本件売買契約締結につきBが無権限であったことにつき対抗を受け、売買契約は無効であるとして本事案における請求は認められないこととなります。
しかし、父の会社(R社)には重過失まではないため、もし通則法4条2項が類推適用されれば、売買契約が締結された地の法(「行為地法」)である日本法(会社法349条4項・5項)が適用される結果、第三者としてBの無権限について対抗を受けず、売買契約は有効であるものとして本事案における請求は認められることとなります。
折角5億円を支払ったので、有力説が裁判所に容れられれば、父の会社(R社)の請求が認められそうで一安心はしました。
…そういえば、本件委任契約の準拠法(甲国法)、及び本件売買契約の準拠法(乙国法)については、どのように考えれば良いのでしょうか?

イメージ共有のため敢て実質法の分野で例えれば、本事案のテーマは「法人の準拠法」ですから、その単位法律関係は「会社法」に属する事項であり、「民法」に属する「法律行為・契約」とは基本的には関係がない、ということになります。
ただ、例えば甲国法(民法等)については、仮にA社からBに対し本事案における越権行為(債務不履行)に基づく損害賠償請求等をする場合には、その準拠法(契約の準拠法)として適用されるでしょうね。念のため、補足までですが。
(4)外国人法
● 外国人法
・ 法人の従属法とは別に、外国人・外国法人等につき規制する各種実質法(民法・会社法の一部条文も含まれる)が存在し、外国人法等と総称される。
【注意】
現時点では、単純化のため、外国人法の観点を捨象した解説をしている。かつ、一般的な学習においては、それで足りる。

それでは、本事案を基にした設例を用いて、間接管轄について学習(復習)しておきましょう。
3.外国判決の承認・執行

【設例】
● 本事案において、R社の弁護士が国際私法に通じていなかったこともあり、R社は敗訴してしまった。
● R社の株主Cは、R社の従たる営業所所在地国(丙国)にR社の取締役Dが大量の金塊を所有しているとの情報を入手し、丙国の裁判所において、Dに対し、本件売買契約締結に関する善管注意義務違反によりR社が損害を被ったとして、株主代表訴訟を提起した。
● 丙国裁判所は、執行可能財産が所在する地であることを管轄原因として国際裁判管轄を認め、かつ準拠法として丙国法(日本の会社法423条に相当する条文)を適用した上で、当該訴訟においてR社(代表者は株主C)の勝訴判決を下した。
● その後、当該金塊は当該訴訟提起の直前に日本に移管されていたことが判明したため、Cは、日本の裁判所において、Dに対し、当該勝訴判決の執行を求める訴えを提起した。
(1)間接管轄(専属管轄)
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
(管轄権の専属)
第三条の五 会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。
2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
3 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。
● 趣旨
(民訴法3条の5第1項が日本の裁判所の専属管轄を認めた趣旨)
同条に挙げられている訴えについては、「法律関係の画一的処理の必要性が高く、日本の裁判所が迅速かつ適正に審理判断すべきである」ため(佐藤=小林・一問一答 102頁)。
【整理】一読すればOK
民訴法3条の5第1項
・ 会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)
・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴え
・ その他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるもの

本設例における株主代表訴訟(会社法847条)に係る訴えは、「会社法第七編第二章」第二節に規定されている訴えですから、民訴法3条の5第1項の規定する例外(「第四節及び第六節」)には該当せず、日本の裁判所が日本の法律(会社法等)を適用して迅速かつ適正に審理判断し画一的処理をすべき法律関係に関する訴えとして、日本の裁判所の専属管轄に属します(民訴法3条の5第1項)。
したがって、その他の要件を検討するまでもなく、丙国裁判所には国際裁判管轄(間接管轄)が認められないため、本設例におけるR社(株主C)の勝訴判決は日本においては承認されません(民訴法118条1号)。

その通りです。
日本の裁判所の専属管轄に関する条項の具体的な機能について、理解ができていますね。
まとめ
1.国際裁判管轄
● 民訴法3条の2第3項
● 民訴法3条の3第4号
● 民訴法3条の3第7号
2.準拠法選択
● 条理
● 通則法4条2項
3.外国判決の承認・執行
● 民訴法118条1号
● 民訴法3条の5第1項

最後に、甲国法等の外国法への向き合い方については、こちらを参照しておいて下さい。
●「外国法(向き合い方)~準拠法として」
それにしても、大量の金塊を備蓄しているとは、お父さんの会社は、かなり手広く商売をされているようですね…
さて、雑談に終始する間に陽が落ちて来ましたが、話を本題に戻すと、国際私法を学ぶことについて決心は固まりましたか?
【第16回】 失踪宣告の準拠法