【第2回】 行為能力の準拠法(1)

…というわけなんです。
Bから薦められ、素敵な時計だったのでつい…。その後の経緯は良く判りません。結果的には敗訴した、とは後で親から聞かされました。
テーマ
1.国際裁判管轄
● 被告住所地等管轄
2.準拠法選択
● 行為能力(年齢による行為能力の制限)の準拠法
3.外国判決の承認・執行
● 間接管轄
事案
● 律子は、高校2年生(17歳)の時、甲国に1ヶ月間留学中、学友B(甲国人・18歳)との間で10万円相当の腕時計(「本件腕時計」)の売買契約(「本件売買契約」)を締結した。
● 代金支払い後に帰国。本件腕時計を親に見せ経緯を話したところ、未成年には高価過ぎるとして、本件売買契約を取り消す方針となった。
● 律子・B双方の親同士の協議が捗らず、結局、日本の裁判所において、B名で律子に対し、本件腕時計の売買代金支払請求の訴えが提起された。
【甲国民法】
「年齢16歳をもって、成年とする。」
【図】日本の裁判所において
B(18歳)→(本件腕時計の売買代金支払請求の訴え)→律子(17歳)
目次
1.国際裁判管轄
(1)被告住所地等
(2)特別の事情
(3)緊急管轄
2.準拠法選択
(1)本国法主義(原則)
(2)国籍・住所・常居所
(3)行為地法の適用(例外)
(4)意思能力
(5)権利能力
3.外国判決の承認・執行
(1)間接管轄
(2)判断基準

本事案も、日本・甲国に跨るため、国際的私法関係に属しますね。
折角お話頂いたことですし、本事案についても、(広義の)国際私法の観点で検討してみましょう。
まず、日本の裁判所の国際裁判管轄については、問題なく認められたでしょうね。
1.国際裁判管轄
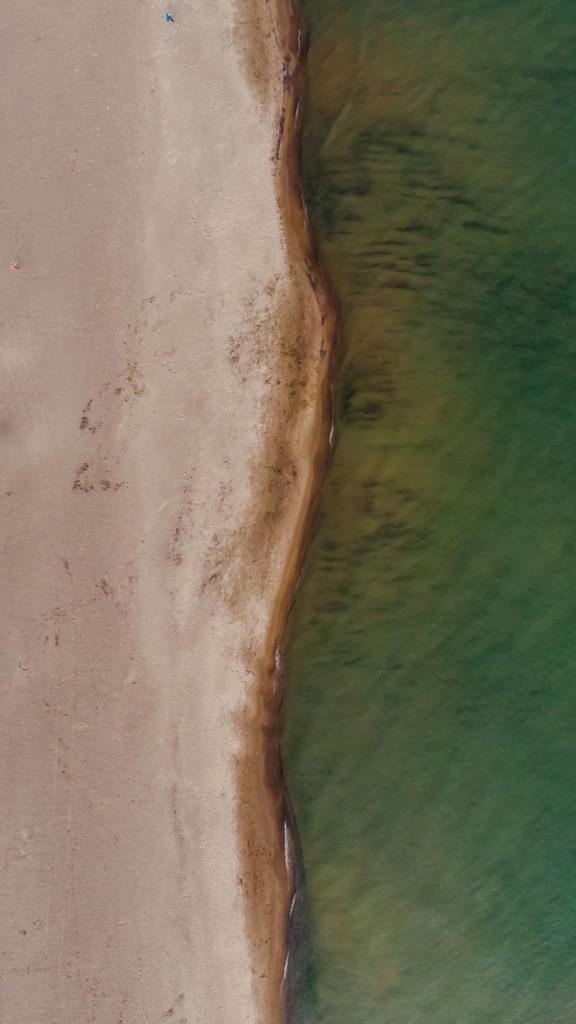
(1)被告住所地等
(被告の住所等による管轄権)
第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2 (略)
3 (略)
● 趣旨
(民訴法3条の2第1項 が「人」(自然人)につき、被告住所地等管轄を規定する趣旨)
国内訴訟に関する規定(民訴法4条1項)同様、「相当な準備をして訴えを提起することができる原告と、不意に訴えを提起されて応訴を余儀なくされる被告との衡平を図る」ことにある(佐藤=小林・一問一答22頁)。

本事案においても、律子さんの住所は日本にあったため、(1)日本の裁判所の国際裁判管轄が認められたのでしょう(3条の2第1項)。
(なお、国際裁判管轄においては、被告にかかる負担から、被告住所地管轄が尚更重要、と言えますね。)
それに加えて、(2)国内土地管轄の有無につき検討され、最終的に律子さんが普通裁判籍(訴えの種類・内容を問わない裁判籍)を有する住所地の管轄(民訴法4条1項・2項)が認められたはずです。
(日本の国際裁判管轄が認められた後、更に日本の国内土地管轄につき決定される点は、この機会に理解しておいて下さい。)
なお、先ほど民訴法3条の2の条文において「(略)」とした同第2項・第3項についても、参考まで触れてはおきます。
(民訴法3条の2第2項は、一読しておけば十分(特別な立場にある日本人に関する規定)。民訴法3条の2第3項は、法人等に関する重要な定めではあるが、現時点では解説を省略。)
(被告の住所等による管轄権)
第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

さて、実は、以前お話した「1つでも管轄原因(民訴法3条の2以下)があれば裁判管轄あり」 の原則(国際裁判管轄・国内裁判管轄に共通)に対し、例外規定(民訴法3条の9(特別の事情による訴えの却下))(国際裁判管轄固有の規定)が存在します。
(2)特別の事情
(特別の事情による訴えの却下)
第三条の九 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
● 趣旨(民訴法3条の9)
国際裁判管轄が問題となる事案において裁量移送(民訴法17条)の制度がないことに照らし、訴えの全部又は一部却下により、当事者間の衡平又は適正かつ迅速な審理の実現を図る
【佐藤=小林・一問一答 157-158頁参照】
● 留意点(民事訴訟法3条の9)
国際裁判管轄に係る裁判所の裁量の余地を大きくし、当事者の予見可能性等を損ねかねない。

本事案については、上記の通り少なくとも1つは国際裁判管轄の管轄原因(民訴法3条の2第1項)が認められることから、特別の事情による訴えの却下が問題となりえます。
しかし、お伺いする限り、該当する特別の事情はないようですね。
他方、民訴法3条の9とは「逆」の規定は置かれてい「ない」点も、この機会に認識しておいて下さい。
(3)緊急管轄
● 根拠・留意点
・民訴法3条の9とは逆に、日本の裁判所の国際裁判管轄(民訴法3条の2以下)が認められない場合において、具体的事情により例外的に国際裁判管轄(「緊急管轄」)を認める規定は置かれていない。
・しかし、条理に基づき、緊急管轄を肯定すべき場合があることも否定はされていない。
・なお、緊急管轄についても、民訴法3条の9同様、 国際裁判管轄に係る裁判所の裁量の余地を大きくし、当事者の予見可能性等を損ねかねない点、同様の問題意識が必要。

冒頭、「結果的には敗訴した、とは後で親から聞かされました。」と言いましたが、聞き間違いをしていたかもしれません。
日本の裁判所の国際裁判管轄が認められた以上、当然日本の民法が適用され、私は当時17歳の未成年(民法4条)だったことから、取消し(民法5条2項)が認められ、私は勝訴(相手方Bの請求棄却)となったはずですよね?

…まだ仕方ありませんが、国際的私法関係の処理に慣れていないようですね…。
別途お話した内容の繰り返しにはなりますが、仮に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められたとしても、常に日本法が適用される訳ではありません。
本事案においては、日本国・甲国いずれかの国の実質法(民法)が準拠法として適用されることになるでしょう。その内容次第では、律子さんの行為能力の有無(成年・未成年の区別)につき結論が異なる可能性があります。その結果、本事案の解決も異なるでしょう。そこで、準拠法選択が問題となります。

そうでした…
2.準拠法選択

(1)本国法主義(原則)
第一節 人
(人の行為能力)
第四条 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 (略)
3 (略)
● 単位法律関係(通則法4条1項)
「人の行為能力」は、年齢に基づく財産的行為能力と解される。
【理由】
1.成年後見・補佐・補助に関しては、別途規定(通則法5条)が設けられている。
2.いわゆる身分行為能力 (例:婚姻能力・認知能力・遺言能力等) 等については、個々の行為自体の準拠法(例えば、遺言能力につき、通則法37条1項に基づく準拠法)によると解される。
● 連結点(通則法4条1項)
国籍
● 準拠法(通則法4条1項)
本国法

ここで、国籍を連結点とする趣旨、及び関係概念につき簡単に解説しておきましょう。
現時点では、凡そのイメージが持てれば十分です。
(2)国籍・住所・常居所
● 属人法
・ 国際私法上、人がどの場所にいても適用される法を「属人法」と言う。
・ 人の能力・身分に関する問題については、属人法を適用することが広く認められている。
・ 属人法に関しては、主に2つの考え方がある(本国法主義と住所地法主義)。
● 本国法主義
国籍を属人法決定の基準とする主義(通則法が採用)。大陸法系諸国が採用。
【メリット】
・ 国家法は、国民の民族・習慣等を考慮して制定されており、各国民と密接な関係を有することが一般的。
・ 安定性(変更が容易ではない)
・ 明確性(各国法上の要件に基づき付与等される)の点で優れている。等
【デメリット】
形骸化(典型例は難民)のおそれ等
● 住所地法主義
住所を属人法決定の基準とする主義。英米法系諸国が採用。
(通則法上、採用されず。「住所」との文言はあるも、連結点としては(※)、使用されていない。)
【メリット】
・ 能力・身分に基づいた個人の日常生活との結び付きが強い。等
【デメリット】
・ 比較的容易に変更可能であり、安定性に欠ける。
・ 国により住所概念は多種多様であり、明確性に欠ける。 等
(※)通則法上、第5条(後見開始の審判等)・第6条(失踪の宣告)においては、「住所」との文言があるが、あくまで(準拠法選択ルールたる通則法としては例外的に)国際裁判管轄原因として使用されているに止まる。なお、ここでの話は、あくまで狭義の国際私法(準拠法選択)上の連結点の話。民訴法上、管轄原因として「住所」が採用されている点については、先述の通り。
● 「常居所」
・ 法廷地が異なれば、国際私法(日本における通則法に相当する法律)が異なる。
・ 国際私法が異なれば、連結点が異なる (国籍・住所のいずれか等となる)。
・ 連結点が異なると、選択される準拠法(実質法)が異なり、その内容・その適用結果次第では、国際的私法関係が左右される(不安定)。
そこで、上記2つの主義の調和の見地から、「常居所」という概念が、「ハーグ国際私法会議」(国際私法の統一を究極的な目的とした国際会議)において事実概念(定義なし)として採択された。通則法も、いくつかの条文で採用している(通則法8条2項・20条等)。

私は日本人ですから、通則法4条1項によると、本事案においても私の本国法である日本国民法(民法4条、民法5条2項)が適用されたのでは?

原則論としては、そうなりそうですね。
しかし、Bの立場に立って考えてみましょう。
本件腕時計の売却相手である律子さんについて、仮に氏名・使用言語その他の事情から(他のアジアの国の国民ではなく)日本人であること、或いは年齢そのものは知りえたとしても、律子さんがその本国法によれば成年なのか否かまでは、知らないのが通常でしょう。
そのような状況を想定し、通則法4条2項が置かれています。
(3)行為地法の適用(例外)
(人の行為能力)
第四条 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3 (略)
● 趣旨(通則法4条2項)
取引保護(小出・一問一答 24頁参照)。
● 連結点(通則法4条2項)
行為地
● 準拠法(通則法4条2項)
行為地法

この場合の連結点は、国際私法上の取引保護のため、法律行為(契約等)の「行為地」とされています。
本事案において、本件売買契約の当時律子さんとBは甲国に居たため、「行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合」に該当しますから、律子さんの行為能力の準拠法としては、行為地法である甲国民法(成人年齢16歳)が適用されたのでしょう。
律子さん(当時17歳)は成年者とみなされた結果、本事案の訴訟においては、そのままBの請求が認められたと考えられます。

私が敗訴した背景には、そういう理屈があったのですね。
…1つ疑問があるのですが。
本事案を離れ、仮に私が19歳(日本国民法によれば成人)の時に、成人年齢20歳の国(当該国の民法上、私は未成年)において同様の取引をしていたら、どうなっていたのでしょうか?

良い質問ですね。
その場合、律子さんは行為地法によれば未成年者ですから、そもそも「行為地法によれば行為能力者となるべきとき」(通則法4条2項)との例外に該当しません。通則法4条2項について検討するまでもなく、原則通り本国法である日本国民法が適用され、律子さんは成年者として扱われます(通則法4条1項) 。
そうだとしても、本国法が適用された律子さんにとり問題はなく、また相手方にとっても基本的には不都合はないでしょうからね。
なお、先ほど通則法4条の条文の中で「(略)」とした同3項についても、参考まで触れてはおきます。
(いずれお話する機会も来るでしょうから、現時点では、一読しておけば十分です(親族・相続、及び不動産に関する特別な規定)。)
(人の行為能力)
第四条 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3 前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。

それでは、準拠法選択の解説の最後に、行為能力の類似概念である意思能力・権利能力につき、簡単に問題意識のみ共有しておきます。
関係概念の全体像を一応示す趣旨ですので、現時点では、聞き流しておいてもらって結構です。
(4)意思能力
● 意思能力
・ 通則法上の明文なし。
・ 通則法4条を類推適用できるか?
(5)権利能力
● 権利能力
・ 通則法上の明文なし。
・ 自然人の権利能力を一般的に否定する国があるとすれば、その国の法を準拠法とすることは法的に許容できないのではないか?
・ 自然人の権利能力に関する個別的な問題(例:不法行為に基づく損害賠償請求権に関する胎児の権利能力等)については、例えば問題となる不法行為自体の準拠法(通則法17条)等、個々の法律関係の準拠法によれば足りるのでは?(権利能力それ自体につき、独立して準拠法を選択する実益はないのでは?)
3.外国判決の承認・執行

【設例】
● (本事案における訴えの替わりに)甲国の裁判所において、Aが、律子さんに対し、本件腕時計の売買代金支払請求の訴えを提起した。

本設例の場合、国際裁判管轄は認められるでしょうか?

???
先程、「2.準拠法選択」の検討が終わりましたよね?
「1.国際裁判管轄」については、更にその前に終えていますが…

…まだまだ仕方ありませんが、国際的私法関係の処理に慣れていないようですね…。
私の質問は、日本ではなく、甲国の裁判所における国際裁判管轄の有無ですよ。

あっ、そうですね。
…しかし、甲国の裁判所の国際裁判管轄(外国法である甲国民事訴訟法等)につき、なぜ検討する必要があるのでしょうか?
先程のお話から、ここで解説の対象となるルール(法源)は、内国法(日本法)に限ると理解していましたが…

よく覚えていましたね(笑)。
先程は民訴法118条全体までは読まなかったかも知れませんが、実は、日本における外国判決の承認・執行の場面においては、外国裁判所における国際裁判管轄の有無が検討対象になるのです。
(1)間接管轄
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
● 趣旨(民訴法118条1号)
過剰な裁判管轄権行使からの被告の保護
(事案とほぼ関連性を有しない裁判所が、過剰に国際裁判管轄権を行使した結果として下された判決は、承認に相応しくない)等。
● 「裁判権」(民訴法118条1号)
一般的に「国際裁判管轄権」を含むものと解されている。
(なお、「裁判権」そのものの意義等については、ここでは立ち入らない。)
● 間接管轄
・ ここで検討する外国裁判所の国際裁判管轄は、一般に「間接管轄」と呼ばれる。
・ 日本の裁判所が、「1.国際裁判管轄」の段階において自ら検討する管轄(「直接管轄」)と区別されている。

判断主体は日本の裁判所だとしても、あくまで甲国の裁判所の国際裁判管轄の有無の問題ですから、甲国民事訴訟法を見なければ判断できないように思われますが…
(2)判断基準
● 間接管轄の判断基準(1)
判決国の基準によるか?日本の基準によるか?
【結論】
日本の基準による( 判例(最判平成26年4月24日)・通説)。
【理由】
そう解さなければ、民訴法118条1号の要件が無意味になる(判決国の基準によるならば、常に「管轄あり」となりかねない。)等。
● 間接管轄の判断基準(2)
日本の基準によるとしても、直接管轄の基準と同一の基準によるのか?
(なお、判例の理解については、下記2つの考え方がある等、争い有り。)
1.同一基準説(通説(「鏡像理論」))
【理由】
・ (承認基準を緩和し)日本の裁判所の直接管轄を否定すべき場合にまで間接管轄を肯定することは、法理論的一貫性を欠く。
・ 基準の明確性等
2.独自基準説(有力説)
【理由】
・ いわゆる身分関係事件等を念頭に、承認基準を緩和すれば国際的私法関係の安定・円滑等に資する。
(ある国際的私法関係につき、国毎に有効・無効が異なる等の事態を回避しうる。)等

現時点では、いわゆる財産権上の訴えを念頭に、また簡単のため、まずは通説(鏡像理論)に依拠して検討しましょう。
(なお、ここで解説対象(ルール(法源))は、基本的には先述の通り内国法(日本法)に限るのですが、上記論点のように、今後も外国法に関連する条文・論点は登場しますので、ご留意ください。。ただ、具体的外国法(例えば、ドイツ法・フランス法・UK法・US法)についての解説はないものとご理解ください。なおなお、一般論として、「ある言語のネイティブでない方が、当該言語以外を使用言語とする外国法について、真の意味で『語る』ことはできない。」と考えています。)
本事案に関して、民訴法3条の2以下を「チェックリスト」的に眺めてみて、甲国裁判所の国際裁判管轄が認められそうですか?

わずか1ヶ月間の留学だったので、私の住所(民訴法3条の2第1項)は甲国にはなかったし…、未成年の留学生だった私が、
甲国に財産(民訴法3条の3第3号)を持っていたはずもないですし…。
該当無しです!

おそらくそうでしょうね。
本事案においては、仮に甲国の裁判所においてBが勝訴判決を得たとしても、日本の民訴法(3条の2以下)の観点からは、 間接管轄(民訴法118条1号)が認められないでしょう。その結果、 当該勝訴判決は日本では承認・執行されないこととなります。
(なお、上述した緊急管轄については、あくまで例外であること、また本設例において格別の事情もなさそうですから、検討する必要はありません。念のため。)
まとめ
1.国際裁判管轄
● 民訴法3条の2第1項・2項・3項
● 民訴法3条の9
● 条理
2.準拠法選択
● 通則法4条1項・2項
3.外国判決の承認・執行
● 民訴法118条1号

最後に、甲国法等の外国法への向き合い方については、こちらを参照しておいて下さい。
●「外国法(向き合い方)~準拠法として」
それにしても、高い授業料でしたね。本件腕時計に今でも相応の価値があれば、高くはないのかも知れませんが。
いずれにしても、国際的な契約に際しての一留意点につき、10代最後に貴重な経験ができてむしろ良かった、ということでしょうか。

実は、本件腕時計は、先日海外旅行に行った時に紛失してしまいました…
国際的な契約と言えば…
【第3回】 契約の準拠法(1)

